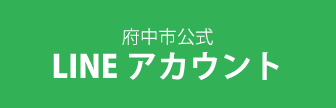手当・支援
特定不妊治療費助成事業【令和4年度経過措置】
体外受精または顕微授精の不妊治療を受けられているご夫婦について、治療費の一部を助成する「不妊治療費助成事業」を行っています。
申請期限は令和5年4月30日としていますが、県の決定通知が遅延した等の理由で申請期限を超過する場合はご連絡ください。 また、県の決定通知を受けて1か月以内に申請してください。
その場合においても申請期限は令和5年6月30日までとなりますのでご注意ください。
助成を受けることができる人
次の要件をすべて満たす人です。
- 申請日時点で婚姻している夫婦(事実婚を含む)であって、双方またはいずれかが府中市に1年以上、実際に居住している人
- 広島県特定不妊治療支援事業の助成の承認決定を受けている人
- 市税等を滞納していない世帯
※1年以上居住していない場合でも、申請時に「申述書」を提出していただき、府中市に定住するなど市長が特に認める場合は、助成を受けることができます。
令和4年4月から特定不妊治療が保険適用になりました
令和4年4月から特定不妊治療が保険適用となったことに伴い、従来の助成制度は令和3年度で終了しましたが、助成制度から保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、「年度をまたぐ1回の治療」については、国の方針に準じた経過措置を実施します。 府中市では、令和4年3月31日までに治療を開始した特定不妊治療について、つぎのとおり助成します。 令和3年度中に開始した治療・広島県特定不妊治療費助成事業については県ホームページで詳細をご確認ください。
助成内容
医療機関で行った体外受精または顕微授精に要した費用(入院や食事代など治療に直接関係のない費用は除く。)に対して、広島県の不妊治療費助成金額を除いた費用のうち、1回25万円を上限とし助成をします。
助成期間及び助成回数は広島県の特定不妊治療支援事業と同じです。
お問い合わせ先・申請場所
■子育て応援課ネウボラ推進室
TEL:0847-44-6688
■上下支所地域共生係
TEL:0847-62-2231
府中市特定不妊治療(生殖補助医療・先進医療)支援事業
府中市では、令和5年4月から不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、生殖補助医療や先進医療等のうち、保険適用または保険適用外となる検査・治療に要した費用の助成を開始しました。
※広島県の制度については、こちらをご覧ください。
助成を受けることができる人
- 治療開始時に婚姻している夫婦※1であって、申請時に府中市内※2に住所を有する者
- 体外受精または顕微授精以外では、妊娠の見込みがないうと医師が判断し、生殖補助医療の保険医療機関で特定不妊治療等※3や先進医療等※4を受けた者
- 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること※5
- 申請する検査に対して、広島県を除く他の自治体の助成を受けていない者
※1 事実婚の方も対象となります。
※2 単身赴任等により、夫婦のいずれか一方のみが市内に住所を有する場合や、申請者が市内に居住している場合は可となります。
※3 本事業において「生殖補助医療」とは、体外受精及び顕微鏡受精等の特定不妊治療並びに特定不妊治療を行うにあたり精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)をいいます。
※4 本事業において、「先進医療等」とは、保険外の先進的な医療技術として認められた治療(医療機関によっては保険診療と組み合わせて実施することができます)や、先進医療会議において審議が行われている技術(保険診療との併用は認められていません)をいいます。
※5 「年齢・回数の特例措置」の対象となる場合があります。
特定不妊治療(生殖補助医療・先進医療)支援事業チラシ(R5〜)
お問い合わせ先・申請場所
■子育て応援課ネウボラ推進室
TEL:0847-44-6688
■上下支所地域共生係
TEL:0847-62-2231
不妊検査費等助成事業
不妊検査および薬物療法や人工授精を含めた一般不妊治療を受けられている夫婦について、費用の一部を助成する「不妊検査費等助成事業」を行っています。
助成を受けることができる人
次の要件を全て満たす人です。
- 治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚を含む)であって、双方またはいずれかが府中市に1年以上、実際に居住している
- 広島県の不妊検査費等助成事業の承認決定がされている人
- 広島県の不妊検査費等助成事業以外の費用助成を受けていない人
※令和5年5月から、市税の納付状況、居住期間による要件は不要としています。
※広島県不妊検査費等助成事業については、こちらをご覧ください。
助成内容・申請について
| 助成対象検査・治療 | 不妊症の診断・治療のための検査・一般不妊治療(体外受精や顕微授精を除く、タイミング療法、薬物療法、人工授精、男性不妊治療等)に要した費用(医療保険適用の有無は問いません) |
| 助成対象 | 助成対象に要した費用の2分の1(上限5万円) ※千円未満切り捨て |
| 助成回数 | 1組の夫婦につき1回助成 |
※助成対象は広島県の不妊検査費等助成事業と同じです。
1.府中市に申請する前に、広島県の不妊検査費助成事業に申請してください。
2.広島県不妊検査費助成事業の助成決定を受けたら、受けた日の翌日から起算して1か月以内に、府中市に書類を提出してください。
お問い合わせ先・申請場所
■子育て応援課ネウボラ推進室
TEL:0847-44-6688
■上下支所地域共生係
TEL:0847-62-2231
府中市不育症検査費用助成事業
令和5年4月から研究段階にある不育症の検査を受けられる方への支援として、助成事業を開始しました。この制度では、先進医療として厚生労働省が定める不育症検査費用の一部を助成しています。
広島県の助成についてはこちらをご覧ください。
助成を受けることができる人
助成対象者は次の要件を全て満たす方です。
- 既往流死産回数が2回以上の者
- 申請時点において、府中市に住所を有する者
- 申請する検査に対して、広島県を除く他の自治体の助成を受けていない者
お問い合わせ先・申請場所
■子育て応援課ネウボラ推進室
TEL:0847-44-6688
■上下支所地域共生係
TEL:0847-62-2231
子育て支援ゴミ袋
指定ごみ袋の支給(2歳未満のこどもがいる世帯に限る)
対象:2歳未満のこどもがいる世帯
【出生】の場合は、生まれた月から満2歳になる前の月まで
【転入】の場合は、転入した月の次の月から満2歳になる前の月まで
支給枚数:対象者1人につき大袋(45リットル)10枚/月
お問い合わせ先
環境整備課
TEL:0847-43-9222
多胎児ひろば
多胎児とその家族が集まっておしゃべりしたり、子育てを楽しむコツやアイデアを話しあったり、情報交換ができるひろばです。多胎児ならでのお話をしたり、ホッとできる時間、楽しい時間を過ごしましょう。
ふれあい遊ぶや絵本の読み聞かせなどもあります。
対象者・開催月
- 府中市に住む多胎児とその家族
- 多胎児妊婦
- 偶数月の第2土曜日
お問い合わせ先
子育て応援課ネウボラ推進室(子育てステーションちゅちゅ)
TEL: 0847-46-2455
ファミリー・サポート事業
子育てを応援してほしい方(依頼会員)と、子育てを応援したい方(提供会員)が、互いに会員となって安心して子育てをするための相互援助活動です。援助を受けることと、行うことの両方を希望する場合は「両方会員」になることができます。会員登録と利用の申し込みは、子育てステーションちゅちゅ(府中天満屋内)で受け付けています。
サポート内容
- 小学校、義務教育学校及び保育施設までの送迎
- 保育施設・小学校・義務教育学校・放課後児童クラブ開始前・終了後の児童の預かり、その他、必要に応じて一時的な預かりなど
注) 会員の事故に備え、補償保険に加入していますので、安心して活動ができます。(保険料は市が負担します)
料金表
| 曜日 | 時間 | 金額 |
|---|---|---|
| 月曜〜金曜 | 7時30分〜20時まで | 600円 / 1時間あたり |
| 土曜・日曜・祝日 | 7時30分〜20時まで | 700円 / 1時間あたり |
お問い合わせ先
子育て応援課ネウボラ推進室(子育てステーションちゅちゅ)
TEL: 0847-46-2455
未熟児養育医療給付事業
未熟児養育医療は、出生持の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟のまま出生した子どもで、指定医療機関に入院し、養育を行う必要がある子どもに対して、医療の給付を行う制度です。所得に応じて費用の一部負担があります。
未熟児養育医療は、出生持の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟のまま出生した子どもで、指定医療機関に入院し、養育を行う必要がある子どもに対して、医療の給付を行う制度です。所得に応じて費用の一部負担があります。
対象者
医師が入院養育の必要を認めた、1歳未満で府中市内に住民票のある未熟児
対象となる医療
入院中の診療、処置、手術、薬剤、治療材料の支給、看護等
お問い合わせ先
子育て応援課ネウボラ推進室
TEL:0847-44-6688
こども医療
令和5年10月に名称が「乳幼児医療費助成制度」から「こども医療費助成制度」に変わります。
対象となる子どもが医療機関において、保険診療を受ける際の自己負担部分(一部負担金を除く。)を助成します。
対象・助成内容
対象の子どもが府中市に住所を有していること
対象の子どもが健康保険に加入していること
| 年齢 | 0歳から満18歳到達後初めての3月末 |
|---|---|
| 助成対象 | 通院・入院 |
一部負担金
県内の医療機関にかかるときは、健康保険証と乳幼児等医療費受給者証を提示して受診し、次の一部負担金を医療機関等の窓口でお支払いください。
| 区分 | 一部負担金 (窓口で一部負担金をお支払いいただく日数) | |
| 保険医療機関 | 医療機関ごとに1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) | |
| 保険医療機関 | 同一医療機関における複数診療科受診 | 医科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) 歯科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) |
| 訪問看護 | 訪問看護事業者ごとに1日500円(月4日まで) | |
| 柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ | 施術所ごとに1日500円(月4日まで) | |
| 保険薬局(院外処方) | 一部負担金なし | |
※保険診療にかかる自己負担額が500円に満たない場合は、その額が1日の負担額です。 ただし、保険薬局(院外処方)は除きます。
申請に必要なもの
・こども医療申請書
・対象の子どもの健康保険証
・【府中市外から転入または未就学児の申請をする場合】申請者(保護者)と対象の子どものマイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類。(マイナンバーの確認が出来ない場合は所得課税証明書)
※マイナンバーが確認できる書類は、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された世帯全員の住民票等です。
※本人確認資料は、マイナンバーカード、運転免許証などになります。(写真付きのものがない場合はお問い合わせください。)
※所得課税証明書の年度は、転入日や対象の子どもの生年月日によって異なります。詳しくは子育て応援課にご確認ください。
申請について
お子さんが出生した場合や他市町から転入した場合には、申請が必要です。
異動日(出生日や転入日等)から14日以内に手続きしてください。申請が遅れると異動日までさかのぼって資格が付かないことがあります。
健康保険証の発行が遅くなるなど、申請に必要な書類が間に合わない場合はお早めに子育て応援課に相談してください。
更新申請
更新手続きは、原則不要です。
未就学児は小学校就学時まで、1歳ごとに更新します。有効期間終了前に新しい受給者証を送付します。
就学時は18歳到達年度末まで受給者証の更新はありません。住所変更等を除き、同じ受給者証を使用します。
現在「乳幼児等医療費受給者証」をお持ちの0歳から15歳の方については、令和6年8月までに随時、新受給者証へ更新します。
有効期限内の「乳幼児等医療費受給者証」は今まで通り使用可能です。
その他手続き
次のいずれかに該当する場合は、こども医療費受給者証、対象の子どもの健康保険証、申請者(保護者、扶養義務者に限る)の本人確認資料を持って速やかに届出を行ってください。
| 届出が必要な場合 | 提出書類 |
| 加入している健康保険証が変わった場合 | 変更届(PDF) |
| 名前が変わった場合 | 変更届(PDF) |
| 住所が変わった場合(市内転居) | 変更届(PDF) |
| 住所が変わった場合(市外転居) | 喪失届(PDF) |
| 受給者証を紛失した場合 | 再交付申請書(PDF) |
医療費の払戻し申請
県外の医療機関で受診したときや、受給者証を忘れて受診したときは、医療費を窓口で一旦支払うことになります。支払った額のうち、保険医療費の自己負担分(かかった医療費の2割または3割)は、市役所で払戻しを受けることができますので、申請してください。 受診された日の翌月以降に、子育て応援課または上下支所の窓口で申請してください(一部負担金の確認が必要なため、1か月単位で申請してください。)。
(申請に必要なもの)
1.償還払い申請書
2.子ども医療費受給者証
3.健康保険証(対象の子どもの名前が記載されたもの)
4.通帳
5.印鑑(認印で可)
6.領収書
領収書には、受診者名・受診日・医療費総額(保険点数)・領収額が記入されているものに限ります。通院の場合は、通院日ごと(入院の場合は入院月ごと)の領収書を月単位でまとめてお持ちください。
お問い合わせ先
子育て応援課 子育て企画係
TEL:0847-43-7139
児童手当
支給対象
中学校・義務教育学校(満15歳以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されます。
手当月額(児童一人につき)
支給額
| 区 分 | |||
1. |
3歳未満 |
15,000円 | |
| 2. |
3歳~小学生・義務教育学校1年生から6年生 | 第1・2子 | 10,000円 |
| 3. |
3歳~小学生・義務教育学校1年生から6年生 | 第3子以降 | 15,000円 |
| 4. |
中学生・義務教育学校7年生から9年生 | 10,000円 | |
| 5. | 所得制限額以上(特例給付) |
5,000円 | |
| 6. | 所得上限額以上(資格喪失) | 支給されません | |
※3歳の誕生日の翌月分から、3歳~小学校・義務教育学校前期課程修了前の額に変わります。
※養育する児童(18歳に達する日以後の3月31日までの間にある者。児童福祉施設等の入所児童を除く。)のうち、年長者から第1子、第2子・・と数えます。
※所得制限限度額以上の場合、中学生以下の児童1人につき一律月額5,000円を支給します。
※所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
所得制限限度額・所得上限限度額について
本年5月までの手当は前年度の所得で判定し、6月分以降の手当は、本年度の所得で判定します。
限度額一覧
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額 | 所得上限限度額 | 収入額 |
| 0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1071.0万円 |
| 1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1124.0万円 |
| 2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1162.0万円 |
| 3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1200.0万円 |
| 4人 | 774.0万円 | 1002.0万円 | 1010.0万円 | 1238.0万円 |
| 5人 | 812.0万円 | 1040.0万円 | 1048.0万円 | 1276.0万円 |
| 6人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
※ 扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
詳細については市のホームページをご確認ください。児童手当について
手当の支給
則として、6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)の各9日に、指定の口座に振り込みします。
※その他必要に応じて必要な書類があります。
※届出・手続きは、事由発生した日から15日以内にお済ませください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ先
子育て応援課 子育て企画係
TEL:0847-43-7139
児童扶養手当
詳しくは、事前にご相談・お問い合わせください。
【問い合わせ先】
子育て応援課 子育て企画係 Tel. 0847-43-7139
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、離婚による母子家庭や父子家庭など父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
支給対象者
年齢が18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)子どもをもつ母子家庭の母、監護し、かつ生計を同じくする父子家庭の父、または当該父母以外の者で子どもを養育する養育者に支給されます。
支給要件
父母が離婚した
母又は父が死亡した
母又は父が一定の障害の状態にある
未婚の子を養育しているなど
※所得制限などにより支給されない場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
手当額(月額)
令和5年4月現在
| 全部支給 | 一部支給 | |
| 児童1人の場合 | 44,140円 | 44,130〜10,410円 |
| 児童2人目の加算額 | 10,420円 |
10,410〜5,210円 |
| 児童3人目からの加算額 | 6,250円 |
6,240〜3,130円 |
所得制限の額
| 扶養親族等数 | 本人全部支給所得額(円) | 本人一部支給所得額(円) | 配偶者、扶養義務者、 孤児等の養育者所得額(円) |
|---|---|---|---|
| 0人 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
| 1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
| 2人 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
| 3人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
| 4人 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
※子どもの父から養育費を母又は子どもが受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。(父の場合も同じ)
詳細については市のホームページをご確認ください。児童扶養手当について
お問い合わせ先
子育て応援課 子育て企画係
TEL:0847-43-7139
特別児童扶養手当
対象
概ね身体障害者手帳1級から3級、または、療育手帳マルA、A、マルBの障害がある20歳未満の児童をもつ父母、または養育者の人に支給されます。
ただし、父母や養育者または扶養義務者の所得によって制限があります。また、障害があることを支給理由とする公的年金を受けていたり、児童福祉施設に入所している場合は、支給されません。
支給額
1級:53,700円(月額) 2級:35,760円(月額)
支払時期
原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支払われます。(11月は当月分まで)
所得制限限度額
所得制限限度額
| 扶養親族等数 | 受給者本人(円) | 配偶者・扶養義務者(円) |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
| 1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
| 2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
| 3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
| 4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
| 5人 | 6,496,000 | 7,388,000 |
| 1人増 | 380,000 | 213,000 |
手続き方法
手当を受けようとする場合には、「認定請求書」の提出が必要になります。
手続きに必要なもの
1.印鑑
2.世帯全員の住民票
3.請求者及び児童の戸籍謄本
4.請求書
5.所得証明書注1)
6.請求者名義の通帳
7.請求者のマイナンバーを確認できる書類、請求者の身元を確認できる書類
※児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーの記入も必要です。
8.この他、必要に応じて書類を求める場合があります。
注1) その年の1月1日に住所がなかった方に限ります。ただし、1月から7月に手続きの場合は、前年の1月1日に住所がなかった人に限ります。
所得状況届の提出
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「所得状況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。既に受給されている人には、8月初旬に案内通知をします。
お問い合わせ先
福祉課 地域福祉係
TEL:0847-43-7148
ひとり親家庭等医療
対象者が医療機関において、保険診療を受ける際の自己負担部分(一部負担金を除く。)を助成します。
対象
府中市に住所を有していること
健康保険に加入していること
18歳以下の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を現に養育している配偶者のいない人とその児童
父母のいない18歳以下の児童
一部負担金
県内の医療機関にかかるときは、健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を提示して受診し、次の一部負担金を医療機関等の窓口でお支払いください。
一部負担金
| 区分 | 一部負担金 (窓口で一部負担金をお支払いいただく日数) | |
| 保険医療機関 | 医療機関ごとに1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) | |
| 保険医療機関 | 同一医療機関における複数診療科受診 | 医科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) 歯科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) |
| 訪問看護 | 訪問看護事業者ごとに1日500円(月4日まで) | |
| 柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ | 施術所ごとに1日500円(月4日まで) | |
| 保険薬局(院外処方) | 一部負担金なし | |
保険診療にかかる自己負担額が500円に満たない場合は、その額が1日の負担額です。 ただし、保険薬局(院外処方)は除きます。
所得制限
本人及び生計を同一にする扶養義務者が所得税非課税であること
申請に必要なもの
申請書健康保険証
印鑑
所得課税証明書(その年の1月2日以降に転入した場合または必要に応じて提出していただきます。)
申請書 (PDF: 108.4KB)
更新申請
更新手続きは、原則不要です。毎年8月1日に所得審査を行い、該当者には新しい受給者証を有効期間終了前に送付します。
なお、所得状況や健康保険証など確認が必要な場合は、個別にお知らせします。
その他手続き
次のいずれかに該当する場合は、印鑑を持って速やかに届出を行ってください。
加入している健康保険証が変わった場合
名前が変わった場合
住所が変わった場合(市外転出・市内転居)
受給者証を紛失した場合
ひとり親家庭等でなくなったとき
変更届 (PDF: 84.4KB)
再交付申請書 (PDF: 70.8KB)
喪失届 (PDF: 74.9KB)
医療費の払戻し申請
県外の医療機関で受診したときや、受給者証を忘れて受診したときは、医療費を窓口で一旦支払うことになります。支払った額のうち、保険医療費の自己負担分(かかった医療費の2割または3割)は、市役所で払戻しを受けることができますので、申請してください。 受診された日の翌月以降に、女性こども課または上下支所の窓口で申請してください(一部負担金の確認が必要なため、1か月単位で申請してください。)
申請に必要なもの
1. 申請書
2. ひとり親家庭等医療費受給者証
3. 健康保険証(受診者の名前が記載されたもの)
4. 通帳
5. 印鑑(認印で可)
6. 領収書
領収書には、受診者名・受診日・医療費総額(保険点数)・領収額が記入されているものに限ります。通院の場合は、通院日ごと(入院の場合は入院月ごと)の領収書を月単位でまとめてお持ちください。
※領収書がない場合は、所定の用紙で医療機関等での証明を受けてください。
申請書 (PDF: 144.6KB)
ベビースケール貸し出し
ベビースケールを無料で貸し出します。
対象:府中市内在住の乳児を養育する保護者
期間:1か月以内(1か月延長あり。最大2か月以内)
お問い合わせ先
■子育て応援課ネウボラ推進室(府中市子育てステーションちゅちゅ)TEL:0847-46-2455
■上下支所地域共生係(府中市子育てステーションふらっと上下)
TEL:0847-62-2231
産前産後ヘルパー派遣事業
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、産前や出産直後の母子に対する心身のケアや家事・育児のサポートを受けやすい環境を整えるため、広島県妊産婦支援事業緊急補助金として、令和6年3月末までの利用料(自己負担額)の半額を助成しています。
利用できる方
府中市内に住民登録をしている世帯で次のいずれかに該当する世帯1.妊娠中で、心身の不調(切迫早産など)があり、家事や育児の支援が必要な世帯
2.産後1年未満で、家事や育児の支援が必要な世帯
※妊娠中の方は原則、診断書が必要となりますが、まずはご相談ください。
内容
- 育児援助:授乳介助、おむつ・衣類交換、沐浴介助、兄姉児の食事介助や遊び相手など(就学前に限る)
- 家事援助
委託事業者
■府中市社会福祉協議会
場所:府中市広谷町919-3(リ・フレ内)
TEL:0847-47-1294 / FAX: 0847-47-1055
■府中市社会福祉協議会 上下支所
場所:府中市上下町上下869-5
TEL:0847-62-2566 / FAX:0847-62-4903
お問い合わせ先
■子育て応援課ネウボラ推進室
TEL:0847-44-6688
■上下支所地域共生係
TEL:0847-62-2231
産後ケア事業
出産後、自宅での生活が始まると、育児や母乳のことなど戸惑うことが多いものです。「産後ケア事業」では、お母さんと赤ちゃんの生活リズムと心身の安定をはかるため、産科医療機関や助産院で、宿泊や日帰りで産後の体調管理や育児サポートを受けることができます。
利用ができる方
府中市に住民票がある産後1年未満のお母さんと赤ちゃんのうち、家族等から十分な家事及び育児等の支援が受けられない人で、産後の体調不良や育児に不安等のある方(※医療の必要な方は利用できません)
ケアの内容
お母さんのケア(こころとからだの相談、乳房の手当、休息)
赤ちゃんのケア(赤ちゃんの健康状態、発育発達の確認)
育児相談、授乳指導、沐浴指導
利用できる日数・時間
宿泊型・・・7日まで、10時から翌日19時まで
日帰り型・・・7日まで、10時から17時まで
食事提供回数
宿泊型・・・1日3食(初日は2食)
日帰り型・・・1食
お問い合わせ先・申請場所
■子育て応援課ネウボラ推進室
TEL:0847-47-6688
■上下支所地域共生係
TEL:0847-62-2231
出産・子育て応援事業(伴走型相談支援と出産・子育て応援ギフト)
核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備に向けて、国は出産・子育て応援交付金を創設しました。府中市では従来から実施している伴走型相談支援を利用された方のうち、令和4年4月1日以降に妊娠届・出生された方を対象に、妊娠届出後に「出産応援ギフト」として妊娠1回につき5万円、出生届出後に「子育て応援ギフト」として子ども1人あたり5万円の支給を、令和5年1月31日から開始しました。
支給内容
- 出産応援ギフト 妊娠1回につき5万円
- 子育て応援ギフト お子さま1人につき5万
支給対象者・申請期限
遡及支給対象者:令和4年4月1日〜令和5年1月30日に子どもが出生または妊娠届出をされた方はこちらをご確認ください。
お問い合わせ先・申請場所
■子育て応援課ネウボラ推進室
TEL:0847-44-6688
■上下支所地域共生係
TEL:0847-62-2231
母乳・ミルク相談
「できれば母乳で育てたいな」、「ミルクをあまり飲んでくれなくて・・・」、「母乳マッサージを利用してみたい」、「おっぱいが詰まりやすいのでどうしたらいいかな」、「体重がどのくらい増えているのか気になるな」など、どんなことでも構いません。まずはご相談ください。
相談方法(要予約)
- 産科や助産院で使用できる「母乳相談等助成券」を使用する
府中市では、母子健康手帳交付時に、母乳相談等助成券(助成額上限2500円)を交付しています。助成券を使用し、母乳相談等助成券裏面又は別紙記載の医療機関や助産院で相談できます。一覧以外の医療機関・助産院では利用することができません。
- 身近な場所で助産師・保健師に相談する(無料)
子育てステーションちゅちゅや子育てステーションふらっと上下で、助産師や保健師に相談することもできます。
なお、母乳マッサージを施術することはできないため、母乳マッサージをご希望の場合は、母乳相談等助成券を利用して医療機関や助産院にご相談ください。
お問い合わせ先
■子育て応援課ネウボラ推進室TEL:0847-44-6688
■上下支所地域共生係
TEL:0847-62-2231
すこやか育児サポート事業(医療機関との連携事業)
府中市、福山市、神石高原町の2市1町では、福山市内の産科医療機関と連携し、妊娠期から妊娠・出産をサポートしています。妊娠や出産について、気がかりなことはありませんか?
まずは、子育て応援課ネウボラ推進室、上下地域共生推進課、かかりつけ産科医療機関にご相談ください。
相談窓口
■子育て応援課ネウボラ推進室
TEL:0847-44-6688
■上下支所地域共生係
TEL:0847-62-2231